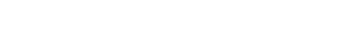令和6年 総務企画委員会(2024.12.13)
【日比たけまさ委員】
本県が発行するグリーンボンドについて伺う。
令和3年11月定例議会代表質問において、安定した資金調達に向けた取組をテーマに質問を行い、その中で、当時注目を集め始めていたESG債についても触れ、県としての今後の取組を伺った。知事からは、ESG債の発行について、メリットやデメリットについて研究を進めるとの答弁があり、その後、様々な検討が重ねられ、1年後の令和4年12月、本県として初めてのグリーンボンド発行に至ったと理解している。
改めて、ESG債とは、環境、エンバイロメント、社会、ソーシャル、ガバナンスの頭文字を取ってつくられた言葉で、環境改善や社会貢献に効果のある事業を資金使途とする債券のことである。SDGsの概念が社会全体に浸透していく中、投資家である企業にとってもESGを重視することは、社会への貢献や信頼獲得といった企業イメージの向上につながるとともに、経営戦略としても社会課題の解決による経営リスクの回避や、新たな事業機会の創出にもつながるものとして、ESG投資への関心は年々高まってきた。こうしたことを背景に、地方債市場においても、年々ESG債の発行規模は右肩上がりに拡大している。
現在、ESG債の中で最も発行額が多いのは、環境面での課題解決を目的としたグリーンボンドである。グリーンボンドの発行額は、令和3年度には6団体で650億円であったものが、昨年度では53団体、3,337億円とこの3年間で大きく増加している。
本県では令和4年度からグリーンボンドを発行しているが、グリーンボンド発行の目的、狙いは何か。
【資金企画課長】
近年、深刻化する気候変動への危機意識の高まりなどを背景として、投資家のESG投資への関心が高まっており、企業や地方公共団体などがグリーンボンドを発行し、資金調達する動きが拡大してきた。
本県においても、そうした状況を踏まえて、投資家層の拡大により安定的な資金調達を実現し、脱炭素社会の実現を見据えた環境改善効果のある事業を着実に推進していくこと、また、本県がカーボンニュートラルの実現に積極的に取り組む姿勢を示すことで、持続可能な地域づくりへの関心を一層高めていくことを主な目的として、2022年度から毎年度継続してグリーンボンドを発行している。
【日比たけまさ委員】
グリーンボンドの発行に当たっては、様々なメリットやデメリットの検討がなされて発行に至ったと思う。そこで、グリーンボンドの発行には具体的にどのようなメリット、そしてデメリットがあるのか。
【資金企画課長】
グリーンボンド発行のメリットは、主に三点挙げられる。
一点目は、グリーンボンドは資金使途を環境改善効果のある事業に限って発行するため、県が環境改善やカーボンニュートラルの実現に取り組む姿勢を分かりやすくアピールできることである。
二点目は、ESG投資の高まりにより、通常の地方債には投資しない投資家であっても、グリーンボンドであることを選好して投資する投資家もおり、投資家層の拡大につながることである。
三点目は、市場環境によっては通常の地方債より低利での発行が可能となることである。通常、地方債は国債の金利に一定の利率を上乗せして発行するが、現在のところグリーンボンドは旺盛な投資家需要を背景に、通常の地方債と比較して上乗せ幅が低く抑えられており、低利での資金調達が可能となっている。
次に、デメリットとしては、資金使途が環境改善効果のある事業に限られるため、多額の発行が難しいことが挙げられる。
【日比たけまさ委員】
グリーンボンドの対象事業は環境改善効果のある事業に限定されるとのことだが、具体的な事業の選定はどのように行っているのか。
【資金企画課長】
本県のグリーンボンドは、市場において適切なグリーンボンドとして受け入れられるため、国際資本市場協会が策定したグリーンボンド原則2021及び環境省が作成したグリーンボンドガイドライン2020年版に適合するよう、調達資金の使途やプロジェクトの評価、選定のプロセスなどについて定めたフレームワークを策定し、第三者機関による外部評価を得た上で発行している。
グリーンボンド原則においては、調達資金の使途として10の事業区分が示されているが、本県では、その中から該当事業のあるエネルギー効率、生物多様性の保全、グリーンビルディング、気候変動への適応などをはじめとした七つの区分を対象としている。
具体的な充当事業の選定に当たっては、起債した翌年度に作成するインパクトレポートにおいて取組実績や具体的な環境改善効果を公表することにしているため、事業効果を明確かつ定量的に示すことができる事業を、各事業を所管する局と調整の上選定しており、2022年度及び2023年度は信号灯器のLED化や貝類増殖場の造成事業、河川のしゅんせつや護岸改修工事などを対象としている。
【日比たけまさ委員】
今年度の本県のグリーンボンドは12月6日に条件決定され、12月20日に発行されると聞いている。これを含めると、これまで3回の発行となるが、それぞれ発行額や投資家の需要の状況、利率などの発行実績はどのようになっているか。
【資金企画課長】
過去3回の本県のグリーンボンドは、いずれも5年の満期一括償還で、発行額は各年度100億円となっている。発行初年度である2022年度は、投資家の需要は発行額100億円に対して約9.8倍の977.3億円が集まり、利率は通常の地方債よりも0.01パーセント低い0.249パーセントとなっている。昨年度は、投資家の需要は発行額100億円に対して約1.6倍の163.7億円、利率は通常の地方債よりも0.02パーセント低い0.477パーセントとなっている。
さらに、先週12月6日に条件決定した今年度は、投資家の需要は発行額100億円に対して約1.5倍の153.6億円、利率は通常の地方債よりも0.02パーセント低い0.809パーセントであり、12月20日に発行予定となっている。
【日比たけまさ委員】
これまでの発行は順調に投資家の需要が集まり、通常の県債より低利で発行できていると理解した。
それでは、現在の債券市場全体を見た場合、グリーンボンドを取り巻く環境はどのようになっているのか、また、課題はどのようなものがあるのか。
【資金企画課長】
現在の債券市場全体を見ると、グリーンボンドをはじめとするESG債の発行団体の増加に伴う供給量の増加により、投資家の選択肢が増えたことなどから、ESG投資ニーズが分散する傾向が見られる。その結果、先ほど答弁したとおり、本県のグリーンボンドの需要倍率も発行初年度と比較すると低下している。
また、発行年限が10年のグリーンボンドでは、他の地方公共団体において投資家の需要が集まらず、当初予定していた発行額から減額発行するケースもあると聞いているほか、本県を含め、地方公共団体44団体が共同で発行するグリーン共同債においては、これまで通常の地方債と比較して0.02パーセント低利での調達ができていたが、11月発行分では0.01パーセントに縮小しているため、今後こうした市場環境の変化に適切に対応していく必要がある。
【日比たけまさ委員】
今、答弁があったように、グリーンボンドを取り巻く環境は少しずつ厳しくなってきていることを理解した。その上で、こうした状況を踏まえ、県として今後どのようにグリーンボンドの発行に取り組んでいくのか。
【資金企画課長】
本県では、これまでも数ある地方債の中から愛知県債を投資家に選んでもらえるよう、格付会社からの格付の取得のほか、本県財政の健全性や本県の環境施策の取組などについて投資家に説明するIR活動を積極的に実施してきた。
また、今年度は新たな取組として、整備費の一部にグリーンボンドにより調達した資金を充当しているSTATION Aiにおいて、投資家を対象としたセミナー型IRを現地視察をかねて実施し、参加者のうち、新規6件を含む10件の投資家を、この12月に発行するグリーンボンドの購入につなげることができた。
グリーンボンドは、環境改善効果のある事業の着実な推進を資金調達の面から支えるとともに、持続可能な地域づくりに向けた機運醸成を図る有効な手段であるため、引き続き、本県がグリーンボンドを発行する意義や事業効果を積極的にPRすることで、投資家需要をしっかりと集め、安定的な資金調達ができるよう取り組んでいきたい。
【日比たけまさ委員】
現在の金融資本市場は、国内外の金融政策の動向をはじめとした先行きの不透明感が強くなっていることから、非常に変動性が高い状況にあり、そうした中、投資家の動向を見極め、市場環境に即した形で県債を発行していくことは大変難しいと思っている。
こうした難しい環境下であっても、県としていかに安定的に資金調達を行っていくかが重要である。他県では、グリーンボンド以外のESG債として、社会課題の解決に資するソーシャルボンド、グリーンまたはソーシャルの課題解決に資するサステナビリティボンド、さらにはサステナビリティの目標達成度合いに応じて条件が変動するサステナビリティ・リンク・ボンドなどを発行している事例もある。
加えて、GX施策推進の起爆剤として期待が高まるGX経済移行債、これは世界初の国によるトランジションボンドであるが、本県は水素社会の実現に向けた様々な取組を実施しているため、この一環として全国発のトランジションボンド発行となると、さらに注目が高まるのではないかと思っている。
引き続き、時宜を捉えて様々な工夫を凝らしながら、調達手段の多様化に取り組むことを要望する。