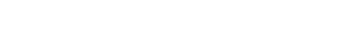令和6年 総務企画委員会(2024.10.7)
【日比たけまさ委員】
県庁組織の持続的な発展を目指すためには、二つの大きな意識の向上が必要である。一つは、安全や健康に働くことができるよう、県庁組織や職員個々人ともに意識の向上を図ること、すなわち身体的・精神的・社会的に良好な状態を指すウェルビーイングの実践である。もう一つは、住民の福祉の増進を図るという地方公共団体としての責務を果たすため、県民に信頼される行政運営を行うこと、すなわちコンプライアンスの徹底である。
ウェルビーイングというと職員の働き方がイメージしやすいと思う。職員に対する健康チェック、心理的安全性やポジティブメンタルヘルスといった心の健康増進、さらには職場や職員の安全意識の徹底が大変重要である。
そこで、職員が心身ともに健康で安心・安全に働けるよう、県としてどのような取組を行っているのか。
【職員厚生課担当課長】
職員の身体の健康について、全職員を対象にした定期健康診断、医師・保健師による保健指導・健康相談など、疾病の早期発見と未然防止に向けた取組を行っている。
心の健康については、ストレスチェックの実施や教育研修、医師・保健師による相談窓口の設置、休職者への職場復帰支援など、メンタルヘルス不調の未然防止・早期発見・再発防止に取り組んでいる。
また、職員が心理的安全性を確保しながら仕事に取り組めるよう、管理監督者向けの研修などを通じ、風通しのよくストレスの少ない職場づくりを進めている。これらの取組は職員のメンタルをネガティブな状態から本来の状態に戻す取組であるため、職員や職場の強みを把握して伸ばすポジティブメンタルヘルスという考え方を、今後の教育研修に取り入れていくことを検討していく。
最後に、職場の安全性の確保については、執務室の照明・温度・落下物の危険など、安全衛生環境について、所属や産業医が定期的に職場巡視を行い、それぞれの課題を把握し、速やかな改善に努めている。
こうした取組により、引き続き職員の心身の健康の保持増進と職場の安全性の確保にしっかり取り組んでいく。
【日比たけまさ委員】
積極的にそうした取組を進めてもらいたい。
次に、コンプライアンスについて伺う。コンプライアンスを訳すと法令遵守だが、実際には法令という範囲にとどまらず、様々な規則、倫理規範を遵守することも含まれる。そこで、今回の質問では、情報漏えい、ハラスメント、内部不正についても触れていく。まず、コンプライアンス全般に関する意識の浸透を図るための研修体制はどのようになっているのか。
【監察室長】
職員のコンプライアンス意識を浸透させるため、繰り返し粘り強く周知していくことが大切である。
このため、まず、新規採用者から幹部級職員まで昇任時などに実施する指名研修において、必ずコンプライアンスや公務員倫理に関する内容を取り扱っている。さらに所属長、各所属で職場研修を担当する班長、新任出納員を対象としたコンプライアンス研修を毎年度実施しているほか、所属単位でも職場研修に取り組んでいる。
また、6月及び12月の職員倫理週間においては、ハラスメント対策や最近の不祥事事例をまとめた職場研修資料を各所属へ送付するとともに、職場またはグループ単位でその資料を活用するなどして倫理研修を実施し、職員の意識醸成を図っている。
こうした取組を絶え間なく行い、職員のコンプライアンス意識を高められるよう努めている。
【日比たけまさ委員】
先日の9月定例議会本会議において、県内企業に対する情報漏えい防止への取組について質問し、警察本部長から主に広報啓発に関する答弁を得た。また、10月4日の総務企画委員会では、先月公表された県の業務委託先における個人情報漏えいの恐れに関する質疑もあった。
仮に県の保有する情報が漏えいした場合は、県民の信用を大きく失うことにつながる。職員による情報漏えい防止やサイバーセキュリティに対する意識向上を図るため、どのような取組を行っているのか。
【情報政策課担当課長】
職員による情報漏えいを防ぐための取組として、USBメモリ等の外部記憶媒体の利用をシステム上制限するとともに、特別に許可を得た場合を除き、データの書き込みを禁止するなどの対策を講じている。
あわせて、職員一人一人の情報セキュリティ意識を高めるため、新規採用時、採用3年目・7年目、役職昇任時といった節目に研修を実施し、情報資産の適正な取扱いをはじめとした、セキュリティ上、遵守すべき事項の周知徹底を行っている。
また、サイバーセキュリティに対する職員の意識向上のための取組として、ウイルス感染や情報漏えい等の原因となる標的型攻撃と呼ばれるサイバー攻撃に備え、不審なメールに対し、職員が常に危機意識を持って適切に対応できるよう攻撃を模した偽メールを職員に送るメール訓練を実施するなどの取組を行っている。
【日比たけまさ委員】
サイバー攻撃も高度化しているため、こうした取組を絶え間なく実施してほしい。また、情報漏えいは、退職時も非常にリスクが伴うため、そうした点も留意してほしい。
昨今、行政や政治に関連したハラスメントについても報道が多く見受けられ、県民からの信用を大きく失っているように感じ、大変残念である。
そこで、ハラスメントに関する研修はどのように行われているのか。また、疑いありを含む、ハラスメントに関する窓口や相談者を守る仕組みというものはどのようになっているのか。あわせて、実際の相談件数を伺う。
【監察室長】
ハラスメントに関する研修について、コンプライアンス研修の中で取り扱っている。例えば、所属長向けには、ハラスメント相談を受けた際の対応方法や注意事項など、一般職員向けにはハラスメントの定義や相談窓口の周知などというように、対象者に合わせた内容となるよう工夫をしている。
相談窓口については、人事課監察室、職員厚生課、各局の主管課、所属長、人事委員会に設置しているほか、公益通報制度の外部窓口を委託している弁護士も相談を受け付けるなど、相談者が相談しやすいよう幅広く設置している。
次に、相談者を守る仕組みについて、各種ハラスメントの防止のため、職員や所属長の責務や相談への対応等を定めた要綱を制定している。その中で、プライバシーの保護や不利益取扱いの防止などの規定を設けている。また、実際に事実確認の調査を行う際には、相談者の意向をしっかり聞き取り、最大限配慮して慎重に行っている。
最後に、ハラスメントに関する相談件数は、昨年度、監察室で受け付けた件数は21件である。
【日比たけまさ委員】
組織内の不正行為は、ないことが一番望ましく、そのためにコンプライアンス意識の強化に努めていると答弁で確認した。
一方で、万が一に不正行為が行われていた場合には早期に発見し、是正を図ることにより、県民からの信用の失墜を防ぐとともに、組織と職員を守ることにつながることから、こうした体制の整備は極めて重要である。
そこで、疑いありを含む内部不正を正す体制、窓口や通報者を守る仕組みはどのようになっているのか。また、実際の通報件数を伺う。
【監察室長】
内部不正を正す体制としては、愛知県職員等公益通報要綱に基づき対応することになる。具体的に、職員等から法令違反行為などに関する内部通報があった場合、公益通報として受理し、事実確認の調査を行った上、その結果に基づく措置を執ることになる。
公益通報の窓口は、内部窓口として人事課監察室、外部窓口として委託した弁護士において設けている。制度上、通報者の情報を知り得ることができるのは、要綱で公益通報管理者となっている人事局長、公益通報調査員である人事管理監、人事課長、人事課監察室の職員、外部窓口の弁護士のみとなっている。
なお、外部窓口の弁護士が公益通報を受けた場合は、公益通報管理者及び公益通報調査員も通報者の情報を知り得ることはない。
通報があり、公益通報の要件に該当する場合は、公益通報者保護法において、通報者への不利益取扱いや通報者を特定する情報の漏えいなどが禁止されており、本県の要綱においても同様の規定を設けている。
最後に、通報件数については、昨年度は2件である。
【日比たけまさ委員】
最後に要望だが、職場に集う全ての人の安全や健康を第一に考える組織、そして、職員一人一人の安全と健康に対し、常に高い意識を持つことが、持続的に発展する組織として最も大切である。
また、憲法第15条第2項に、すべて公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、そして、地方自治法第1条の2第1項には、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとある。職員、そして、議員は、このコンプライアンスに対して、より高い意識を持たなければならないと思う。
様々な取組が行われていることは確認できたが、常に高い意識を持ち続けるためには、こうした問題について短時間でも頻繁に考える機会を設けることが必要である。例えば、朝礼の時間を活用した気づきの発表や短時間の複数回にわたる学習の実践など、これまで以上に高い意識づけができるような取組の強化を要望する。